私はよくグリーン車を利用します。
その理由は、
・鉄道の仕事をさせてもらっているから。
・交通機関の人間として、サービスを見るため。
・体が成長してふつうの座席ではきつくなってきたから。
・日帰り出張での疲れを軽減するため。
・静かな車内に身を置きたいから。
などなど、いろいろありますが、一番大きな理由は、若いころは高嶺の花だったグリーン車が、料金的にはあまり気にならなくなってきたからかもしれません。
だから、プライベートで乗るときは普通車ですが、仕事で鉄道を利用する場合は、快速電車でもグリーン車に乗るようにしています。
ホームで電車を待っているときに、「座れるかどうか。」などということに、あまり神経を使う必要もなくなれば、精神的に余裕が出てくるというのも事実です。
私はこのような理由でグリーン車を利用するのですが、そんな私がグリーン車に乗るたびにいつも思うことがあります。
それは、「グリーン車って何だろう?」ということです。
グリーン車って何なのでしょうか?
何のために利用者は運賃、特急料金にプラスして高額のグリーン料金を支払うのでしょうか?
その理由は、「隔離された空間で、座席がゆったりしているから。」です。
実は、それ以外には何もないんです。
本当に何もない。
驚くほど簡素化されたサービスというか、究極のサービスとは何か。もちろん下限の究極ですが、つまり、何もしないんです。
まるでいすみ鉄道のキャッチコピーのようですね。
つまり、ドリンクサービスも、食事のサービスも、ネットもWiFiも、新聞もアメニティーも何もない。
無料サービスじゃなくて良いから、お金を払うから何か飲み物がほしい、そう思っても、一部の列車以外には車内販売すらない。
ただ、普通席に比べると座席がゆったりとしていて、背もたれが倒れる角度がちょっと大きい程度。
座席だけなんです。
つまり、グリーン車というのはハードだけを提供するサービスで、ソフト面でのサービス、おもてなしという意味での心遣いはゼロ。
そして、その座席に座らせていただく料金が、運賃、特急料金にさらにプラスして払う数千円のグリーン料金なのです。
では、その座席がどれだけ素晴らしいかというと、大したことはない。
いまどきニトリだってこのぐらいのソファ売ってるよ、という程度の座席がほとんどで、田舎の方へ行くと都会のお古の車両が走っていますから、グリーン車の座席だって20年以上前のものだったりします。
私は不思議なんですよ。
おもてなしの何もない上級サービス。
「いったい誰が乗るのだろう。」
案の定、グリーン車って、いつもたいてい空いています。
普通車指定席から満席になって行って、グリーン車は最後に満席になります。
座席がゆったりしていますから、1両あたりの乗車定員が少ないにもかかわらず、最後まで空いている。
自虐的には、「だからグリーン車なんですよ。いつでも座席が取れますから。」ということなのかもしれませんが、私はなんだか違うなあと思います。


先日、鹿児島から宮崎まで乗った特急「きりしま」のグリーン車。
確かに座席はゆったりしているけど、ただそれだけ。
他には何もありません。
この時の乗車人員は定員11席に対して4名。
私は、「ほう、4名も乗っているんだ。」と驚いたほどです。
JR九州でさえこういう状況ですから、他社などは惨憺たるものです。

こちらはこの春に網走から旭川まで乗車した特急「大雪」のグリーン車。
網走を出たときには乗客は私1名。
北見であと2名乗り込んできて、終点の旭川まで3名でした。
指定席の方は4割ほど乗っていたと思いますが、グリーン車は3名でした。
ということは、どういうことかというと、人気のない商品なのです。
九州から北海道まで、グリーン車って人気がない商品。
どうして人気がないかと言えば、Value for Money ではないから。
つまり、払ったお金に対する価値がないんです。
でも、旧国鉄系の鉄道会社って、基本的には全国どこも同じDNAが流れているから、全国どこもグリーン車って同じ状況で、つまり、何のホスピタリティーもない。でも、高額なグリーン料金をチャージできるから、会社としてはありがたい存在なんです。
だって、国鉄のころからのお古の車両を連結しておくだけで、何もサービスしなくたって、余分にお金が入ってくるんだから、商売をやる側にとってみたら、こんなに良いことはありませんよね。
でも、世の中そんなに甘くはありませんから、それが利用者数という数字に表れてくる。
でもって、車両更新の時期を見計らって、新型車両に置き換えられるとグリーン車はなくなるんです。
お客様が乗らないから、無くなる。
これも共通のDNA。
お客様に乗っていただく努力を何もしないで、乗らないのはお客の責任だから、廃止します。
全国共通のこの統一が取れた企業見解は実に見事です。
見上げた民間会社です。
そう、我々が見上げるということは、彼らは上から目線で、見下しているんです。利用者を。
何もしなくたって、お客は乗るだろうと。
そして、その理由は、DNAだからなんです。
だから、国鉄時代を知らない若い社員にも脈々と受け継がれていく。
私は、30年経過した今こそこのDNAを断ち切らないと、この国の輸送は、いずれ立ち行かなくなる。
少なくとも地域をまたいだ鉄道輸送というのは、近い将来ダメになると考えているのです。
実際に、貨物輸送にそれが露呈しておりますがね。
高級商品というのは、憧れの商品であり、それだけの価値があるものです。
上質の商品から売れるようにしていくのが商売の極意であり、たとえ売れなかったとしても、客寄せになるような、そういう商品が高級商品なのであって、これが民間会社のDNAなのです。
では、JRの最高級商品って何でしょうか?
金持ち専用の豪華列車は別として、時刻表に載っている誰でも利用できる列車としての最高商品って、「グランクラス」です。
そのグランクラスでは、アテンダントが乗車して、お飲物もお食事もアメニティーも、各種サービスが取り揃えられています。
サービスの内容には賛否両論がありますが、まあ、JRとしては努力しているし、よく考えたと思います。
ところが、その後がいけない。
何がいけないかというと、「グランクラス料金:A」と「グランクラス料金:B」ってのがある。
Aはアテンダントが乗車してフルサービスをする。Bは何もサービスがない「シートのみ」のサービス。
そして、その差は区間にもよりますが、Bの方がAよりも2000円ほど安い。
「何もサービスがありませんから2000円安くなっています。」
って、罪の意識を感じているようですが、これは間違いなんです。
なぜならば、アテンダントが乗車して、お食事をサービスして、お飲物をサービスして、アメニティーをご用意する。
これは2000円分ですと宣言しちゃっているからなんです。
つまり、あとは座席の料金ですよってことを自分で言っちゃってるんです。
そうするとお客はどうなるか。
なんでこんなに小さな弁当が2000円なんだ、ってことになる。
お客様がお支払いするサービス料金というのは、そういうものではないのです。
トータルに考えて、すべてのサービスが揃って初めてグランクラスであって、それがブランドなのです。
旧国鉄系の会社の人たちは、皆さん優秀で最高学府を出ているにもかかわらず、全国共通でそういうことがわかっていないから、あるいは中にはわかっている人がいるかもしれないけれど、そういう人が言い出せない、抜擢されない、言いだした途端に外される。たぶん会社の中はそういうことになっているのでしょうけど、それがつまりはDNAなのです。
では、航空会社はどうするか。
自社のファーストやビジネスはブランドと考えていますから、空港に到着したところからおもてなしが始まります。
カウンターの列に並ばなくてもよい。
出発前にはゆったりとくつろげるラウンジがある。
国際線の場合、飛行機に乗ったら機内食が出るのは当たり前ですが、にもかかわらず、ラウンジでは豪華な食事が出て、お酒も出る。
飛行機に乗るのも並ばなくて済むし、機内はもちろんゆったりした座席。
新聞、雑誌、お酒、お飲物、機内販売、映画、WiFiなど、退屈させないおもてなしが各種あって、目的地に到着したら預けた荷物が最優先で返却されて、サービスによっては空港の出口に黒塗りの車が待っていて、市内のホテルまで無料で運んでくれる。
こういう一連のトータルサービスが「ブランド」なんです。
でも、航空会社でも、会社側の都合でビジネスクラスやファーストクラスの正式なサービスができないことがあります。
つまり、座席だけのサービスの場合ですが、そういう時に航空会社はどうしているかというと、その座席をエコノミーに開放するんです。
つまり一般座席としてお客様にお乗りいただく。
国内線でもファーストクラスが設定されている路線、東京、札幌、大阪、福岡、沖縄以外の路線に、飛行機の運用変更などでファーストクラスが付いた飛行機が使われることがあります。
そういう時はどうなるかと言えば、ファーストの座席がその下のクラスJの座席として開放されます。
つまり、ファーストのサービスができなければ、ファーストではないということで、座席というのはサービスの一部でしかありませんから、その座席だけ良いからとって、ファースト料金を取ることはできないと考えている。これが航空会社です。
これに対して鉄道会社は、「グランクラス、グリーン車は車内清掃が終わりましたので、グランクラス、グリーン車のお客様は最初に車内にお入りください。」なんてことすらやっていない。
当然出発前のラウンジなんてありませんから、発車時刻の3分5分前までむせ返るような、あるいは寒風吹きすさぶホームで待たせておいて、やっと乗った瞬間に「車内販売はありませんのでご了承ください。」
お客様は皆同じ。サービスも何もないのも同じ。違うのは切符の料金だけっていうのが鉄道会社のやり方なんですね。
航空会社だったら、シートのみのサービスのグランクラスの編成が運用に入るなら、グランクラスの車両をグリーン車にしますよ。
そうすれば、そういう半端な列車(つまり区間運転の列車)はグリーン車から先に埋まっていくのではないでしょうか。
だって、お客様としてはお得感満載ですからね。
お客様は得した気分になる。
これがお客様から見た Value for Money ということですから。
お客様に「得しちゃった。」と思わせなければリピーターにはなりませんよね。
車内販売はない。自動販売機も使用停止。途中駅で買う時間もない。
かと言えば駅でもなんでもないところで「反対列車待ち合わせのために5分停車します。」
だったら手前の駅でその分停めて、お客様の便宜を図れよ。
自社で儲からないからやらないんだったら地元の事業者に駅構内を開放して、駅弁でも何でも売らせろよ。
ふつうだったら、みんなそう思いますが、こういうのがいわゆる優等列車というやつですから、
「自分たちのやり方が気に食わなければ、お乗りいただかなくて結構ですよ。」
と言っているようなもの。
グリーン車どころか、普通座席だって、もう2度と乗りません。
これが、お客様の結論です。
今の鉄道会社には、航空会社のDNAを注入しなければならないのです。
なぜなら、航空会社と鉄道会社の両方を経験してみると、そういうことがわかるのです。
ああ、グリーン車。
されど、グリーン車。
私だったら、乗車定員を半分にして、フルフラットの個室感覚にして、お食事もお飲物も配っちゃいますよ。
売ろうなんて考えなくたって、グリーン料金に含まれていると考えればよいのですから。
だって、どうせ3~5人しか乗らないのですからね。
1つだけ確実に言えることは、そのぐらいのことをやらないと、バスに負けるということなのです。
そして、そのバスは、いずれ運転する人がいなくなると言われているのですから、私は鉄道にとって、今は復権の大きなチャンスだと思っているのです。

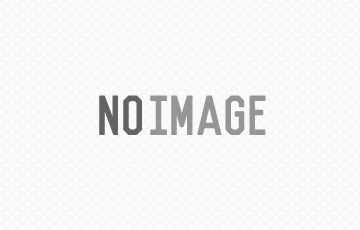





最近のコメント